自動車技術関連セッション
※プログラム内容(スピーカ、コーディネータ、発表テーマ、内容等)が変更になる事がありますので予めご了承ください。

コーディネータ (敬称略)
7月13日(水)
13:30~16:20

- 藤本 博志
- 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授
1
トヨタ初のBEV専用P/F用パワートレーン技術
- 新開発BEVシステムの狙いと概要
- ユニットの新技術
- 今後の展開と課題
- 山本 雅哉
- トヨタ自動車㈱ 電動パワトレ開発統括部 主幹
2
日産アリアの新型パワートレインシステムの開発
- 上質な走行性能を実現する巻線界磁モータ
- 室内空間拡大に貢献するコンパクトパワートレイン
- フラットフロア、充電性能向上を実現するバッテリー
- 池田 伸
- 日産自動車㈱ パワートレイン・EVプロジェクトマネージメント部 主担
3
走行中非接触給電に向けたデンソーの取り組み
- 走行中非接触給電の課題と解決策
- タイヤ内へのコイル配置による電力伝送性能向上効果
- まとめと今後の課題
- 角谷 勇人
- ㈱デンソー まちづくりシステム開発部 担当係長
世界中の自動車メーカが電気自動車(EV)化へ急激に舵を切る中、ハイブリッド車・電気自動車の量産化をそれぞれ約20年・10年以上前に開始していた我が国のカーメーカの技術は、世界をリードし続けている。本セッションでは、トヨタ・日産・デンソーの研究開発をリードするキーパーソンに集結をして頂き、EVパワエレ技術の最新動向と将来展望を語って頂く。
トヨタ自動車・山本様からは今年の5月に発売されたばかりの新型SUV電気自動車bZ4Xで採用された、トヨタ初の電気自動車専用プラットフォーム用パワートレーン技術について熱くご解説頂く。まず、その新開発システムの狙いと概要を俯瞰して頂き、そのユニットで採用された新技術を大いに語って頂く。また現状の課題をご共有頂いた後に、今後将来的に期待される新技術開発の方向性を語って頂けるであろう。
また日産自動車・池田様からは、やはり今年の5月に発売されたばかりの新型EVアリアで採用された新型ワートレインシステムの開発をご説明頂く。世界市場を牽引してきたLEAFを始め殆どのEVはモータの回転子に永久磁石を埋め込んでいるが、なんと新型EVアリアでは、永久磁石を使わないモータを採用し我々専門家を驚かせた。なぜ「巻線界磁モータ」の採用に至ったのか、是非聴講してほしい。
このように国内メーカも次々と素晴らしいEVを発売しているが、EVの航続距離の問題を解決する解として、世界中がEVへの走行中給電の実証試験にしのぎを削っている。そこで最後に角谷様からは、デンソーが長年この夢の技術に対して挑戦してきた技術内容、その課題と解決策を惜しみなくご説明いただく。さらにその究極技術として、産学連携で開発を進めている「タイヤ内に受電コイルを配置した走行中給電システム」をご紹介いただく。この技術は夢ではなく、十分に実現可能であることを実感して頂けるであろう。
このように本セッションは日本を代表する三社が単に集結するだけではなく、パワエレ(電源)・モータ・制御というEV時代の三大キーテクノロジーが、上質な走りや快適な室内空間、無限の航続距離など、いかに商品性の向上に貢献できるかを肌で感じて頂きたい。7/13のオンライン講演で感銘を受けた皆様には、是非7/22に会場にお越し頂き、講演者と対面で議論を楽しんで頂きたい。
※電源システム技術シンポジウムD2セッションとの共通プログラムです。
7月14日(木)
9:30~12:50

- 山本 真義
- 名古屋大学 未来材料・システム研究所 大学院 工学研究科 電気工学専攻 教授
1
宏光MINI EV用バッテリ充電器ユニットの分解解析から見る、中国EVの車載電源設計動向
- 中国製のバッテリ充電器、DC-DCコンバーター、J/B一体ユニット
- 堅実ながらもコストダウンを意識した設計
- 作りやすさを考慮した構造
- 永吉 謙一
- ㈱豊田自動織機 エレクトロニクス事業部 技術部 先行開発室 グループ長
2
車載用パワーエレクトロニクスにおける磁性部品の高性能化とその応用事例
- 車載用磁気部品の応用事例
- インダクタ応用技術
- トランス応用技術
- 今岡 淳
- 名古屋大学 未来材料・システム研究所 准教授
3
車載用48V-DCリンクコンデンサモジュールと、その熱解析事例
- ハイブリッドコンデンサを使用した48V-DCリンクコンデンサモジュール
- 熱解析結果の確からしさの検証(シミュレーション v.s. 実測)
- コンデンサモジュールの寿命予測の一例
- 玉井 裕也
- 日本ケミコン㈱ 技術本部 技術開発部 技術開発二グループ 主管
4
アルミ電解コンデンサの電気・熱マルチドメインモデルについて
- アルミ電解コンデンサのマルチドメインモデルについて
- 燃料噴射装置システムシミュレーションへの実装とその評価結果
- 今後の課題について
本セッションでは宏光MINI EVに搭載されたバッテリー充電器(OBC)とDC-DCコンバータ(96V→12V)の分解解説を最初に行う。そしてそこに搭載されたパワー半導体、キャパシタ(平滑用・フィルタ用)・磁気部品(インダクタ・トランス・フィルタ用)の応用状況を確認する。その後、次世代小型EV並びに大きな市場を持つ中型以上EVに必要なOBC並びにDC-DCコンバータに要求される受動素子の性能指標を議論する。
さらに、磁気部品、キャパシタの双方の最新技術動向を紹介し、車載用としての次世代受動素子応用技術の応用・システム視点からの最前線技術の共有を行う。
※電源システム技術シンポジウムD3セッションとの共通プログラムです。
7月20日(水)
10:00~12:45
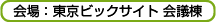
- 本間 正
- オリエンタルモーター㈱ 鶴岡カンパニー AC・BLモーター事業部 開発部 モーター開発担当課長
1
電動車用駆動モータ技術
- トヨタのこれまでの電動車用駆動モータ技術の紹介
- CNに向けたモータ技術
- 滝澤 敬次
- トヨタ自動車㈱ CN先行開発センター CN開発部 CN駆動・EHV開発室 室長
2
プラグインハイブリッドシステムの進化
- カーボンニュートラルへ向けた社会動向とPHEVの技術的な価値
- プラグインハイブリッドシステムの進化
- 電動化による新たな価値
- 半田 和功
- 三菱自動車工業㈱ 第一EV・パワートレイン技術開発本部 チーフ・パワートレイン・エキスパート
3
エレクトリック G-ベクタリング コントロールプラスの開発
- G-Vectoring Controlの概要紹介
- 最初に適用したエンジン車への効果
- EV(MX-30)に適用した際の効果
- 小川 大策
- マツダ㈱ 統合制御システム開発本部 電子基盤開発部 社員
地球温暖化を防止するためにCO2排出低減の必要性がより一層高まっていますが、その対応策として自動車の分野では電動化がますます進行しています。
電動化システムには多くの取り組みがありますが、その中で今回は最前線の自動車メーカーの方々よりEV/HEV/PHEVといった様々な方法についてご講演をいただくことになりました。
燃費・電費向上に関する技術や、電動化を有効利用した操縦安定性向上技術など興味深い内容をご説明いただきます。多分野のモータ関係者にとりまして有意義な内容となっておりますので、この機会をご活用いただけたら幸いです。
※モータ技術シンポジウムB1セッションとの共通プログラムです。
7月20日(水)
14:15~17:00
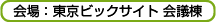
- 車両要求事項とE-Axle最新市場動向
- 高性能E-Axleを実現するモータ・インバータ・ギヤBOX
- 出力密度改良モデル
- 上村 清
- ㈱明電舎 EVグループ EV営業・技術本部 開発第一部 ドライブ開発第二課 課長
2
EV/PHEV向けトラクションモータの開発
- モータの小型化技術
- モータの軽量化技術
- モータの冷却技術
- 上田 智哉
- 日本電産㈱ 中央モーター基礎技術研究所 先進駆動システム開発グループ 上級研究員(グループリーダー)
3
汎用電動駆動ユニットの開発 E3-Drive Technology®
- 汎用電動駆動ユニットの開発
- 適用事例のご紹介
- 商品化に向けての取組と課題
EVの普及拡大に向けてパワートレインの開発競争が激化しております。本セッションで取り上げるE-Axleは、モータ・インバータ・ギアをユニットとして一体化した構成で、モータそのものの技術はもちろんですが、モータ・インバータ配置方法や冷却方法に特徴が出る技術です。ぜひ各社の考え方を聞いていただき、今後のEV普及拡大に役立てていただければ幸いです。
※モータ技術シンポジウムB3セッションとの共通プログラムです。
7月21日(木)
10:00~12:45
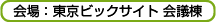
- 阿部 貴志
- 長崎大学 大学院 工学研究科 電気・情報科学部門 電気電子工学分野 教授
1
新型ARIYAの電動パワートレイン
- 新型電気自動車 NISSAN ARIYAの紹介
- 搭載される電動パワートレイン概要
- 駆動用巻線界磁モータの紹介
- 大木 俊治
- 日産自動車㈱ パワートレイン・EV技術開発本部 エキスパートリーダ
2
自動車駆動用巻線界磁モータ
- 巻線界磁モータの特徴
- PMモータとの性能比較
- 自動車用途課題への取り組み
- 桜井 茂夫
- ㈱明電舎 研究開発本部 製品技術研究所 コアテクノロジ開発部 EV先行開発課 主任
3
自動車・産業用途の巻線界磁モータの構造、制御における技術動向
- 自動車用途の巻線界磁モータの構造、制御
- 産業用途の巻線界磁モータの構造、制御
- 巻線界磁モータの可能性
2050年カーボンニュートラルに向け、自動車駆動用モータにはコストと資材の問題や制御性能までも考慮した上で、効率の最大化が要求されています。現状の埋込型永久磁石モータに迫る、もしくはそれ以上の性能を持ち、資材問題をクリアできる様々なモータが研究、開発されています。本セッションでは、巻線界磁モータに焦点を当て、日産自動車株式会社の大木俊治様、株式会社明電舎の桜井茂夫様、静岡大学の青山真大様に講師をお願いし、新型ARIYAの電動パワートレインのご紹介、巻線界磁モータの特徴や永久磁石モータとの性能比較や課題への取り組み、巻線界磁モータの構造と制御そして可能性についてご講演頂きます。
※モータ技術シンポジウムB5セッションとの共通プログラムです。
7月22日(金)
14:15~17:00
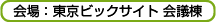
- 報道のミスリード
- バッテリー生産能力の現状
- LCAとカーボンプライシングを導入するとどうなるか?
- 日本のポテンシャル
- まとめ
2
カーボンニュートラルに向けた自動二輪車のパワートレイン戦略
- 製品魅力を上げ、顧客の電動化製品購入Affordabilityを上げる
- 製品カテゴリーに適合したパワートレイン戦略
- 電池への期待
- 松田 義基
- カワサキモータ―ス㈱ 理事 / 技術本部 副本部長
3
カーボンニュートラルに向けたトヨタの取り組み ~バイポーラ構造を持つニッケル水素電池の新規開発~
- カーボンニュートラルに向けたトヨタの取り組み
- BEV/FCEV
- HEV
・バイポーラ構造を持つニッケル水素電池の新規開発
- 奥村 素宜
- トヨタ自動車㈱ 先行電池開発部 グループマネージャー
地球温暖化対策としての脱炭素社会の実現に向け、一段と強化された各国の環境規制がけん引する形で、電動化シフトに向けた技術開発が加速されており、自動車業界を中心に、100年に一度の大変革期を迎えている。
一方で、急激な電動化シフトは、バッテリの需要と供給バランスの崩れや、資源リスクの増大等、解決しなければならない様々な課題も新たに発生している。
本セッションでは、カーボンニュートラルに対応したモビリティーの電動化をテーマに、急激な電動化に対して起こっていることを多角的に捉えると共に、二輪、四輪それぞれのカーボンニュートラルに向けた技術開発の取り組みについて解説いただきます。
※バッテリー技術シンポジウムE2セッションとの共通プログラムです。
7月28日(木)
9:30~12:20

- SiCインバーターの実装応用状況(IONIQ 5)
- 超低インダクタンスパワー半導体モジュール実装応用状況(タイカン、e-tron)
- 次世代実装(SiC&超低L)インバーターにおける問題点とその最新対策技術
- 山本 真義
- 名古屋大学 未来材料・システム研究所 / 大学院 工学研究科 電気工学専攻 教授
2
自動車コンポーネント EMC国際規格の現状と今後の動向
- 自動車コンポーネントEMC国際規格の体系について
- 自動車コンポーネントEMC国際規格の概要
- 自動車コンポーネントEMC国際規格の今後の動向について
- 杉本 久憲
- (一社)KEC関西電子工業振興センター 試験事業部 EMC安全技術グループ EMC第2チーム 主事
3
電動化社会を支えるEMC技術
- 船戸 裕樹
- ㈱日立製作所 研究開発グループ 生産・モノづくりイノベーションセインタ 回路システム研究部 部長
カーボンニュートラルにむけモビリティの電動化が急速に進められている。ドライブトレインの電動化は電磁ノイズの原因となり、これによる問題が生じないようにEMCの国際規格が定められており、コンポーネントや車両はそれに対応する必要がある。
本論では、自動車メーカで異なるEMCの設計概念を、実車の分解からひも解く。また自動車コンポーネントのEMC国際規格を概観し、EMC開発を実現するためのモデル化や解析手法について論じる。
※EMC設計・対策技術シンポジウムG4セッションとの共通プログラムです。
9月15日(木)
9:30~12:20

- 熊野 豊
- パナソニックオートモーティブシステムズ㈱ HMIシステムズ事業部 ディスプレイビジネスユニット シニアエンジニア
1
車載用パワー半導体の高速・高精度な熱・ノイズシミュレーション技術
- 当社のMBD活動紹介と活用方向性
- 高速・高精度を実現するモデル縮退技術
- 熱&EMI検証への応用
- 岡野 資睦
-
東芝デバイス&ストレージ㈱ デバイス&ストレージ研究開発センター パッケージソリューション技術開発部 フェロー
2
車載電子製品の熱設計の考え方 ~インバータを事例に~
- 車載電子製品における熱設計のポイントは、放熱設計(熱伝達)と熱分離(熱絶縁・耐熱)
- 熱設計は、製品信頼性と直結、具体的には熱ー実装信頼性技術
- 熱設計は、あくまで車両の付加価値を高めるのが目的
- 神谷 有弘
- ㈱デンソー 電子PFハードウェア開発部
3
パワーエレクトロニクスシステムにおける損失と熱のシミュレーション
- 自動車・航空機の電動化におけるパワエレの重要性
- 高いスイッチング周波数駆動におけるシステムシミュレーションの考え方
- パワエレシステムにおけるコア、スイッチングデバイス損失と熱の推定
昨今、半導体の高発熱密度化、筐体の小型化、ファンレス化等々により、電子機器の熱設計の難易度が飛躍的に向上し、熱シミュレーションを活用した熱設計が一般的となってきました。しかしながら熱シミュレーションの導入だけでは、熱設計の支援にはなり得ず、その使い方が非常に重要となっています。
本セッションでは、近年のトレンドとなっているMBD(モデルベース開発)、また熱だけでなく電気との連成解析、さらには熱と品質との関係について、業界のスペシャリストにご講演いただきます。
今後の熱設計業務の参考になれば幸いです。
※熱設計・対策技術シンポジウムF5セッションとの共通プログラムです。
9月15日(木)
13:30~16:20

- 三輪 誠
- ㈱豊田自動織機 エレクトロニクス事業部 技術部 開発統括室 人材育成グループ 主査
1
電気自動車の熱マネージメント技術と普及へ向けた課題
- 空調暖房に使える排熱源をもたない駆動源車両での空調システムとは
- 低温環境対応技術や効率改善技術とは
- 将来の電池での空調システムとは
2
発熱量の高精度見積りに必要となるパワーデバイスの実践的モデリング
- 高電圧/大電流を制御するEV環境では熱問題が顕在化し、開発の初期段階から熱対策設計が求められています。本セミナーでは、EVシステム内における発熱量の高精度見積りに必要となるパワーデバイスの実践的モデリングについて解説します。
3
ガソリンエンジンECU技術を電動製品への応用
- 自動車の長期信頼性技術
- 制御とアクチュエータの組み合わせノウハウ
- ECU内部、素子配置による熱放熱効率化
- 近江 慶太
- ㈱デンソー エレクトロニクス技術1部 第1設計室 室長
EV化は既定路線となり、加速するばかりですが、EVにおいて熱問題は今後も注目されることと思われます。本セッションでは、EVの熱問題に焦点を当て、EVにおける熱マネージメントやEVに必須であるパワーデバイスの高精度発熱予測、ガソリンエンジンECUのEVへの応用の3テーマについてご講演して頂きます。
※熱設計・対策技術シンポジウムF6セッションとの共通プログラムです。




































