第30回 バッテリー技術シンポジウム
※プログラム内容(スピーカ、コーディネータ、発表テーマ、内容等)が変更になる事がありますので予めご了承ください。

コーディネータ (敬称略)
7月22日(金)
10:00~12:45
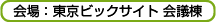
- 田中 善章
- ㈱矢野経済研究所 インダストリアルテクノロジーユニット デバイス&マシナリー産業グループ マネージャー
1
xEVへの期待と電池の技術・市場動向
- xEVのx種と電池に求められる特性
- 電池の技術動向(材料、構造、システム等)
- 電池業界の動向(新規参入の動向等)
- 雨堤 徹
- Amaz技術コンサルティング(合) 代表社員
2
LiB部材市場の現状と今後の展望
- LiB用部材の中で、特に主要四部材である正極材、負極材、電解液、セパレータを対象に、LiB側の市場動向、アプリケーション市場動向を踏まえた上で、部材市場の現状と今後の展望についてお話致します。
- 田中 善章
- ㈱矢野経済研究所 インダストリアルテクノロジーユニット デバイス&マシナリー産業グループ マネージャー
3
EVシフトの本質と周辺産業へのインパクト
- EVシフトの背景と将来展望
- EVシフトが日本にもたらすインパクト
- 見え始めた構造変化の兆し
- 風間 智英
- ㈱野村総合研究所 コンサルティング事業本部 パートナー
「カーボンニュートラル」、「サスティナブル」といったキーワードを伴う車両電動化の流れの中、注目度が高まるLIB市場の動向を踏まえつつ、LiB用部材市場、特に主要四部材である正極材、負極材、電解液、セパレータを対象に、市場動向、今後の展望等についてお話し致します。
7月22日(金)
14:15~17:00
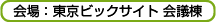
- 報道のミスリード
- バッテリー生産能力の現状
- LCAとカーボンプライシングを導入するとどうなるか?
- 日本のポテンシャル
- まとめ
2
カーボンニュートラルに向けた自動二輪車のパワートレイン戦略
- 製品魅力を上げ、顧客の電動化製品購入Affordabilityを上げる
- 製品カテゴリーに適合したパワートレイン戦略
- 電池への期待
- 松田 義基
- カワサキモータ―ス㈱ 理事 / 技術本部 副本部長
3
カーボンニュートラルに向けたトヨタの取り組み ~バイポーラ構造を持つニッケル水素電池の新規開発~
- カーボンニュートラルに向けたトヨタの取り組み
- BEV/FCEV
- HEV
・バイポーラ構造を持つニッケル水素電池の新規開発
- 奥村 素宜
- トヨタ自動車㈱ 先行電池開発部 グループマネージャー
地球温暖化対策としての脱炭素社会の実現に向け、一段と強化された各国の環境規制がけん引する形で、電動化シフトに向けた技術開発が加速されており、自動車業界を中心に、100年に一度の大変革期を迎えている。
一方で、急激な電動化シフトは、バッテリの需要と供給バランスの崩れや、資源リスクの増大等、解決しなければならない様々な課題も新たに発生している。
本セッションでは、カーボンニュートラルに対応したモビリティーの電動化をテーマに、急激な電動化に対して起こっていることを多角的に捉えると共に、二輪、四輪それぞれのカーボンニュートラルに向けた技術開発の取り組みについて解説いただきます。
※自動車技術関連セッションE2セッションとの共通プログラムです。
8月25日(木)
9:00~11:50

- 石川 正司
- 関西大学 化学生命工学部 化学・物質工学科 教授 / イノベーション創生センター長
1
ロームのIoT向けソリューションの紹介
- IoTに必須な電池メーカーとの協業の紹介
- 無線給電ソリューションの紹介
- 無線ソリューションの紹介
- 進化するNano seriesの紹介
- 梅本 清貴
- ローム㈱ 商品戦略部 商品戦略グループ 課長
2
高耐熱リチウムイオンキャパシタと適用アプリケーション
- 高出力デバイスの必要性
- 高耐熱リチウムイオンキャパシタ - 耐久性能と安全性
- 適用アプリケーション例
- 三尾 巧美
- ㈱ジェイテクト 蓄電デバイス事業部 蓄電デバイス開発室 室長
3
高速作動・高耐久性蓄電デバイスの開発状況
- リチウムイオンキャパシタの特長
- 高速作動・高耐久性のメカニズム
- 次世代蓄電池への期待
- 安東 信雄
- 武蔵エナジーソリューションズ㈱ 開発部 部長
IoT社会への急速な展開により、スモール蓄電技術に関わるビジネスが成長しようとしています。さらに、モビリティー社会をはじめとするこれからの電気エネルギーのアウトプットでは、大電流のやりとりが可能な、高耐久性蓄電デバイスの必要性が高まっています。本セッションでは、従来の単なる大エネルギー貯蔵には収まらない、このような新開拓されつつあるアクティブな蓄電技術とその周辺技術について、指針を示せる講師陣を用意いたしました。今ホットな新局面の蓄電技術とそのビジネス展望をわかりやすく解説します。
8月25日(木)
12:15~15:05

- 山田 將之
- マクセル㈱ 新事業統括本部 電池イノベーション部 部長
1
錯体水素化物イオン伝導体の開発と次世代蓄電池への応用
- 錯体水素化物系リチウム超イオン伝導体の開発
- 多価(マグネシウム・カルシウム)イオン伝導体への展開
- 錯体水素化物を塩として用いた電解液と多価蓄電池への応用
2
全固体ハロゲン化物イオン移動型電池の開発
- 全固体フッ化物電池について
- 全固体塩化物電池について
- 全固体臭化物電池について
3
酸化物固体電解質材料および固体電池の開発
- Li7La3Zr2O12系固体電解質(LLZ)の開発
- LLZを用いた非焼結型電解質の開発
- 電解質材料の固体電池への適用と評価
8月25日(木)
15:30~18:20

- 永峰 政幸
- (国研)物質・材料研究機構 先進蓄電池開発拠点 拠点マネージャー / 信州大学 工学部 特任教授
1
次世代電池の開発状況
- 次世代蓄電池技術の概要
- 元素戦略と新電池
- 液系電池に残された将来性
- 石川 正司
-
関西大学 化学生命工学部 化学・物質工学科 教授 / イノベーション創生センター長
2
水溶液を電解液に用いた超安全リチウムイオン二次電池の開発状況
- 東芝の水系リチウムイオン二次電池の特徴
- 想定される水系リチウムイオン二次電池の用途
- 水系リチウムイオン二次電池製品化に向けた課題と取り組み
3
全固体Naイオン二次電池の開発と今後の展望
- 脱炭素社会に貢献する次世代新電池について
- 資源や環境規制の現状と課題
- 全固体電池の開発コンセプト
- 山内 英郎
- 日本電気硝子㈱ 開発部 グループリーダー
1991年に商品化されたリチウムイオン電池は改良や高性能化を重ね、我々の生活を取巻く様々なシーンに大きな変革をもたらした。いまやこの電池のない日常は想像すら難しい。今後もIoT、EV、航空宇宙、定置用などさらに広範囲な展開が期待され、高エネルギー密度化に限らず、新たな使用環境に適した電池の登場が望まれる。注目度の高い全固体電池もソリューションの一つといえる。
一方、昨今の世界情勢を考えると希少金属資源や石油化学に頼る技術だけでなく、元素戦略を踏まえた高性能電池の開発も急務である。このセッションでは従来のリチウムイオン電池の延長線上から脱却した次世代電池の全体像を把握いただき、具体的事例で最先端技術を紹介する。
8月26日(金)
9:30~12:20

- レドックスフロー電池の原理と特徴
- レドックスフロー電池の活用事例
- 課題と今後の展望
- 柴田 俊和
- 住友電気工業㈱ エネルギーシステム事業開発部 RF電池部長
2
大型蓄電池システム試験評価施設(NLAB)の紹介と試験事例
- NITEの概要
- 大型蓄電池システム試験評価施設(NLAB)のご紹介
- NLABの独自試験技術について
- 五十崎 義之
- (独)製品評価技術基盤機構 国際評価技術本部 蓄電池評価センター センター長
3
カーボンニュートラルの実現に向けた定置用蓄電システムへの期待
- 定置用蓄電システムを取り巻く現状
- 普及拡大に向けた取り組み
- CNの実現に向けた定置用蓄電システムへの期待
- 北條 喜洋
- 経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギーシステム課 係長
カーボンニュートラル実現には、再生可能エネルギーの大量導入と電化推進が重要になる。これらを合わせて進めることで実現できる。そのためには、需要協調と系統安定化が必要となる。そこで、キーとなるのが二次電池を利用した電力貯蔵技術である。
再生可能エネルギー導入が進む北海道では、系統安定化のためにレドックスフロー電池が増設された。一方で、二次電池の課題は安全性の確保である。特に可燃性電解液を用いるリチウムイオン電池の安全性への対策・評価試験方法の確立は、最も重要な課題といえる。
カーボンニュートラル社会実現に向けて、二次電池技術は大きな期待をもって研究開発が進んでいる。国の政策でもキーテクノロジーとして二次電池は位置づけられている。定置用電池電力貯蔵システムの活用が期待されている。
8月26日(金)
13:30~16:20

- 岡田 重人
- 九州大学 グリーンテクノロジー研究教育センター 特任教授 / 名誉教授
1
ナトリウムイオン電池の開発最前線
- ナトリウムを蓄電利用する特徴
- 電極材料の開発動向と大容量化技術
- 最近の実用化の動きと今後の展望
2
リチウムイオン電池リサイクルの現状と課題
- 資源循環とカーボンニュートラル
- LiBのサステナビリティ
- LiBリサイクルの現状と新規技術の紹介
- LiBリサイクルの今後の課題
- 所 千晴
- 早稲田大学 理工学術院 教授 / 東京大学 大学院 工学系研究科 教授
- コバルトなどの金属資源サプライチェーンの未来展望
- レアメタルフリー化を指向したマグネシウム電池開発
- 金属資源サプライチェーンリスクを回避した次世代電池の展望
直接証拠がないとはいえ、炭酸ガスが地球温暖化の主犯であるとの前提が主要各国の共通認識となり、遅ればせながら、我が国も2050年までのゼロエミッション宣言国となりました。この国際公約実現のため、炭酸ガス発生源の20%を占める運輸セクターの炭酸ガス発生源であるガソリン車は日本を含む諸外国が2035年までに新車販売を禁止する政策を打ち出し、今まさに自動車業界は100年に1度の大変革、EVシフトの真っ只中にあります。しかし、鉄の塊であるガソリン車に対し、リチウムイオン電池で動くEVはレアメタルを多用するため、走行時のカーボンフットプリント(CO2排出量)は少ないものの製造時のマテリアルフットプリント(消費天然資源量)はむしろ環境パラドックスを抱えています。そこで本セッションでは、このジレンマ解消の切り札として、エコフレンドリーなポストリチウムイオン電池の開発やリチウムイオン電池のリサイクル技術によるサーキュラーエコノミーソリューションに焦点を当てました。まずポストリチウムイオン電池の最有力候補として、ナトリウムイオン電池の開発状況を東京理科大学駒場慎一教授に、またリチウムイオン電池のリサイクル技術を早稲田大学所千晴教授に、さらに、リチウムイオン電池におけるバッテリーメタルのサプライチェーンについて東北大学本間格教授に解説いただき、EVを取り巻く環境パラドックス解消の可能性を多角的に探ります。



























