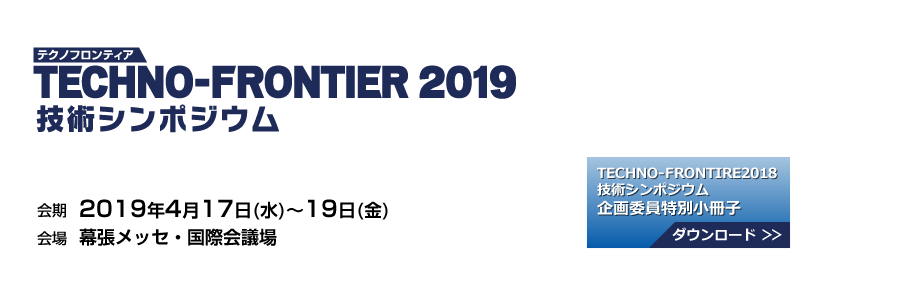※プログラム内容(スピーカ、コーディネータ、発表テーマ、内容等)が変更になる事がありますので予めご了承ください。

コーディネータ (敬称略)
国峯 尚樹
㈱サーマルデザインラボ 代表取締役
1
そもそも熱とは?:新人技術者や理系ではない人向けの超!基本講座
- 熱と温度はどう違う? : エネルギー保存則からのおさらい
- 冷却機構ってなに? : 熱を運ぶ3つの方法
- 熱設計ってどうやるの? :「熱設計」と「熱対策」の違い
鳳 康宏
㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメント
HW設計部門 メカ設計部 部長
2
熱設計簡単ステップ:熱設計で使う公式と使い方をやさしく説明
- 定量化を行うための武器 ~熱流体と電気回路のアナロジー~
- 熱流体のイメージングトレーニング
- 熱設計における熱流体現象の定量化の「要点」
福江 高志
金沢工業大学 基礎教育部 講師
3現場で使える熱設計:熱設計の手順と定石
- 熱設計の進め方(熱抵抗と熱流束であたりをつける)
- 実装要件から放熱経路と熱対策を選び、部品の熱対策仕訳を行う
- 冷却デバイス・放熱材料使いこなし(ファン・ヒートシンク・TIM)
国峯 尚樹
㈱サーマルデザインラボ 代表取締役
熱は身近な現象であり、感覚でとらえることができます。しかし定量化しようとすると極端に難しくなります。このため、設計上流ステージではあまり熱を考慮せず、「シミュレーションや試作評価で温度が高かったら対策を行う」という「後出しのスキーム」が定着しています。こうしたスキームを変えて熱設計の上流化を進めるには、①伝熱現象を正しく理解すること、②手計算レベルである程度定量化できること、③熱設計の流れや定石を知っておくこと、が必要条件になります。
本セッションではやさしい熱設計の解説で定評のある3人の講師を招き、チュートリアルを企画しました。はじめて熱設計に取り組む方、伝熱計算式の熱設計への適用方法を知りたい方、熱設計方法・フローを知りたい方などに最適なセッションとなっています。
F2知らなきゃ損する電子機器の熱規格
熊野 豊
パナソニック㈱ インダストリアルシステムズ社 解析サポート部
主幹技師
1
熱を評価するものさしを創る ― 半導体パッケージの熱モデル規格 ―
- パッケージ「詳細」モデルの満たす必要条件とは
- 過渡熱を視るパッケージ熱等価回路モデルの提案
- JEITA熱設計技術サブコミッティの展望
宮﨑 研
㈱IDAJ 技術担当課長
2JEITA LEDパッケージの熱規格
- ED-4912A改定内容の紹介
- LEDにおける熱抵抗 ~他電子部品との違い~
- より正確に接合部温度を算出する方法とは?
平本 亜紀
スタンレー電気㈱ 光半導体事業部 第二技術部 設計三課
3JEITA サーマルマネジメント標準化動向
- 実装形態の変遷により部品規格が設計情報にはならなくなった
- 大気放熱型熱設計から基板放熱型熱設計へ
- JEITAによる基板放熱型熱設計のためのインフラストラクチャー整備
平沢 浩一
KOA㈱ 技術イニシアティブ 技創りセンター 職人
4JPCA 高放熱基板規格
- 高輝度LED用回路基板規格概要
- 自動車電装及びパワーモジュール用高放熱性電子回路基板規格概要
- まとめ及び今後の展開
米村 直己
デンカ㈱ 電子・先端プロダクツ部門 電子部材部 主幹
近年、電子機器の軽薄短小化、半導体の高発熱密度化、ファンレス化等々により、熱設計の難易度が飛躍的に向上し、設計段階における温度管理が非常に重要になってきました。このトレンドに対し、JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)やJPCA(一般社団法人日本電子回路工業会)では、設計時に正確に温度を測定する方法や、高精度に温度を見積もる方法の規格化を進めています。
今回はJEITAおよびJPCAに参画している技術者をお呼びし、最新の熱規格についてご紹介いただきます。無償で使用することができる規格情報を、是非この講演で入手いただき、日頃の熱設計業務に活かしていただければ幸いです。
F3活用しよう冷却デバイス
魏 杰
富士通アドバンストテクノロジ㈱ 実装技術統括部
システム実装技術部 部長
1薄型サーマルソリューション関連技術
- ヒートパイプの薄型化
- トップヒート姿勢に強いヒートパイプ
- 今後の薄型ソリューション
川原 洋司
㈱フジクラ サーマルテックビジネスユニット技術部 開発グループ
グループ長
2村田製作所の超薄型ベーパーチャンバーの開発
- 村田製作所の超薄型ベーパーチャンバーのご紹介
- モバイル機器の熱問題への導入効果とソリューションのご提案
- 今後の展望
若岡 拓生
㈱村田製作所 事業インキュベーションセンター 新商品事業化推進部
シニアエンジニア
3ループヒートパイプの研究開発動向と用途拡大への挑戦
- LHPのしくみと特長
- LHPの研究開発動向と技術課題
- 超薄型化、長距離化、高熱流束化、大熱量化への挑戦
長野 方星
名古屋大学大学院 工学研究科 機械システム工学専攻 教授
4リチウムイオン電池の異常発熱時における冷却システムの実証実験
- 薄型ヒートパイプと相変化材料を用いて試作した電気自動車向けの電池冷却システムの評価
- リチウムイオン電池セルを外部短絡することで異常発熱を模擬
- 数値シミュレーションを用いてシステム内各部の温度の時間的変化も考察
小野 直樹
芝浦工業大学 工学部 機械機能工学科 教授
ヒートパイプは、従来材料の特性限界を超えた最も効率的高性能な伝熱部品として、宇宙機器から建築産業にも幅広く活用されてあります。一方、ICT装置や車載機器の高密度実装に伴い、より小型または超薄型且つ高密度発熱を処理できる熱伝導・冷却デバイスが要求されてあり、ヒートパイプでの対応可否に対して、厳しいチャレンジを臨みながら大きな適用拡大チャンスとも考えられます。本セッションでは、第一線の研究者と技術者の方々により、薄型ヒートパイプを中心とする最先端技術動向および開発状況を始め、パイプ型や平面型、ループ型を含む様々な適用分析と設計事例をご紹介頂きますので、非常に有益な技術交流を期待できると考えます。
F4小型軽量化を実現する材料
富村 寿夫
元 熊本大学 大学院 先端科学研究部 教授
1超柔軟放熱材料「熱ゴム®」の開発
- TIMの現状
- 千代田インテグレの取り組み
- 熱ゴム®の開発と応用
河野 謙太郎
千代田インテグレ㈱ 開発センター 商品開発室 主任
2放熱材料の設計と信頼性評価
- 放熱材料の概要
- 放熱材料の低熱抵抗化への取り組み
- 信頼性評価に関して
伊藤 崇則
信越化学工業㈱ シリコーン電子材料技術研究所
3
エネルギー変換を革新する未利用熱活用熱電変換モジュール
- 熱電変換技術の概要
- 熱電変換材料の高性能化に向けた取組み
- 熱電変換モジュールのIoTデバイス用電源への適用例
早川 純
㈱日立製作所 基礎研究センタ 主管研究員
高密度実装化された電子機器の熱設計・対策において、合理的かつ効果的な放熱技術の確立は、電子部品の長寿命・高信頼性を確保する上で必要不可欠となっています。本セッションでは、開発・設計の第一線でご活躍の専門家の方々にお集まりいただき、「超柔軟放熱材料「熱ゴム」の開発」、「放熱材料の設計と信頼性評価」、「エネルギー変換を確信する未利用熱活用熱電変換モジュール」という3つの切り口から、基礎的な技術事項だけでなく、応用例、適用例また先進的な取組みなど、有用な最新情報を、関連分野でご活動中の皆様にご提供いたします。
F5電動化における熱設計(カーエレ・パワエレ)
三輪 誠
㈱豊田自動織機 エレクトロニクス事業部 技術部 開発統括室 室長
1車載電子製品の実装・熱設計技術
- 車両の電動化、電子化の加速により車載搭載システムが増加
- 燃費向上のために電子製品には、小型化とさらに高信頼性を求められている
- 熱設計は、小型実装と高信頼性実現の両方を実現するように進化している
神谷 有弘
㈱デンソー 基盤ハードウェア開発部
2シミュレーションによるモータの熱と騒音の検討
- 顧客ニーズの多様化に伴い、モータは本来の性能に加え低騒音化も重要
- 空冷方式モータの低騒音化には、騒音とトレードオフとなる熱の考慮も必要
- シミュレーションにて構造を検討し、機能試作機にて効果を確認
金子 公寿
富士電機㈱ 技術開発本部 イノベーション創出センター
デジタルエンジニアリング部 主査
3JMAG-Designerを使用した高調波損失計算と、
FloTHERMを使用した熱流体解析の連携による、車載モータの発熱計算手法
- モータ制御による電流高調波を考慮した鉄損解析
- JMAG-Designerにより出力された損失分布を熱ソースとして利用
- FloTHERM (XT) による熱流体解析
河治 学
アイシン精機㈱ 走行安全技術部
益々加速化する電動化への対応及び小型化への要求に対し、熱対策は様々な要因が複雑に絡み合い、単独での解決が大変困難になっており、特にカーエレ・パワエレ分野ではその傾向が顕著に現れています。
本セッションでは、「電動化における熱設計」と題して、カーエレ・パワエレ分野で必要とする小型高信頼性の両立とモータの発熱対策をテーマに3名の方に設計者の立場でお話しして頂きます。
上記3事例をご参考にして頂き、現状の問題解決の一助になれば幸いです。
※自動車技術関連セッションF5セッションとの共通プログラムです。
F6知っておこう計測技術
石塚 勝
前 富山県立大学 学長 工学博士
1グリースレス接触面の熱抵抗評価技術
- うねりのある異種固体界面への橘・佐野川の式の適用と課題
- 感圧シートによる圧力分布測定と接触熱抵抗への変換
- 過渡熱抵抗測定による妥当性検証の紹介
青木 洋稔
KOA㈱ 技術IV 技創りC 評価技術開発G
2パナソニックCNS社における熱設計強化の取組み
- 設計に生かせるCFDの開発に取組んできて、多くの商品の開発プロセスに定着している。
- 熱設計の高度化に向けて、発熱量測定装置および熱デバイス開発にも取り組んでいる。
- ワンストップ解決に向け、堅牢・振動音響・EMI・静電気・無線・人体などにも取組んでいる。
岩田 進裕
パナソニック㈱ コネクティッドソリューションズ社
イノベーションセンター 設計ソリューション開発部 技術総括
3ハンダクラック率を熱抵抗測定で検知する最新技術
- 自動車エレクトロニクスにおける信頼性を向上するT3Sterの熱抵抗測定
- デンソー製センサEnergy Eyeによる熱密度を測定
- 熱抵抗値の差異による実装基板上のハンダクラック率の測定方法
篠田 卓也
㈱デンソー 基盤ハードウェア開発部 構造技術開発室 開発1課 担当係長
4産業用電子機器の信頼性向上を目指した冷却性能診断法
- 冷却性能低下の検出だけでなく,その原因を高精度に特定
- 温度センサーを実装していない場所の温度も把握可能
- 状況に応じた的確なメンテナンスに期待
鈴木 智之
㈱東芝 研究開発センター 研究主務
機器の熱設計・熱対策も設計・対策期間の短縮化のほかに質の向上を求められている。そのために、熱設計段階でCFDのような熱流体解析技術の利用が行われている。そこで、昔からの課題は、解析値と実験値がどこまで一致するかということである。しかし、ここにきて、解析技術の発展から、逆に計測の精度はどこまであるのかという問題も顕在化してきた。これは機器の熱設計・熱対策にとって大事なキーポイントである。
このセッションでは計測技術として、接触熱抵抗、熱設計対応力強化の取り組み、ハンダクラック検知技術、冷却法に診断法に焦点を当てた。様々な観点から計測技術を利用した熱設計向上の試みを学んでいただきたい。