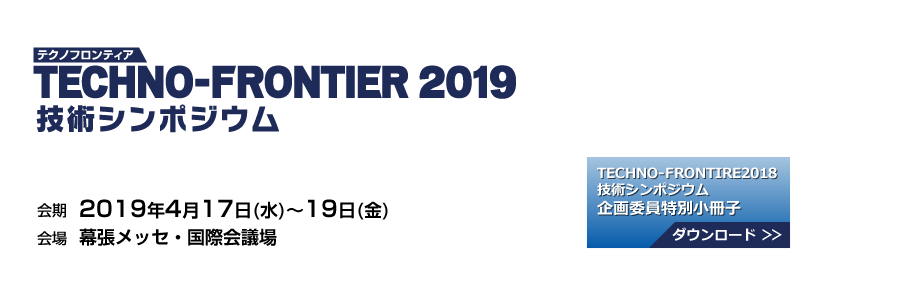※プログラム内容(スピーカ、コーディネータ、発表テーマ、内容等)が変更になる事がありますので予めご了承ください。

コーディネータ (敬称略)
白木 康博
三菱電機㈱ 先端技術総合研究所 電機システム技術部 主席研究員
1
高速パワー半導体デバイス時代のノイズ抑制へ挑戦 ― アクティブ・パッシブフィルタ ―
- SiCやGaNを用いたパワエレ機器から発生するノイズの広帯域化
- パッシブフィルタによるノイズ対策
- アクティブフィルタによるノイズ対策
小笠原 悟司
北海道大学 大学院 情報科学研究院 教授
2パワエレ回路の平衡化によるコモンモード伝導ノイズ相殺技術
- パワエレ回路の主回路部の平衡化技術
- 平衡化技術の適用例
- 平衡化技術のメリット
庄山 正仁
九州大学 大学院システム情報科学研究院 教授
3インバータエアコンにおけるEMS解析と対策事例
- インバータエアコンのEMC解析概要
- EMS(雷サージ)解析技術
- EMS(雷サージ)解析・対策事例
田中 三博
ダイキン工業㈱ テクノロジー・イノベーション・センター
パワエレ機器のノイズ対策技術として、従来からのパッシブフィルタに加えて、アクティブフィルタや波形制御による平衡化技術が注目されてます。また、伝導エミッションや放射エミッション以外のイミュニティ対策も重要となりつつあります。
本セッションでは、まず回路的に非常に複雑なアクティブフィルタについてその必要性、基本原理、応用例をわかりやすく紹介します。次に、ノイズ電流をキャンセルする波形制御により伝導ノイズを低減する技術を紹介します。最後に、設計段階で雷に対するイミュニティの予測技術、対策技術について紹介します。
G2パワエレ機器のノイズ測定・評価技術
玉手 道雄
富士電機㈱ 技術開発本部 先端技術研究所
エネルギー技術研究センター 電気エネルギー技術研究部
電磁応用技術Gr. マネージャー 博士(工学)
1SiCパワーモジュールにおける電磁ノイズ源の特性評価
- 配線インダクタンスの評価(実測・電磁界解析)
- SiCパワーモジュールのスイッチング特性評価
- 同期近傍磁界強度測定に基づくモジュール内雑音電流分布の動的可視化
井渕 貴章
大阪大学 大学院 工学研究科 電気電子情報工学専攻
2
パワーデバイスのスイッチングノイズ評価技術と抑制法
- スイッチングシミュレーションによるノイズ発生メカニズム分析
- デバイス内外における抑制法
- 電源回路での対策の実例
安住 壮紀
㈱東芝 生産技術センター 制御技術研究部 研究主務
3パワーエレクトロニクス応用機器のノイズ測定・評価の注意点
- 電源線伝導妨害測定におけるAMNの影響や基準金属面との距離による影響について
- 放射妨害電界強度測定再現性と測定の注意点について
- 雷サージ試験におけるチョークコイルによる印加波形への影響について
峯松 育弥
(一社)KEC関西電子工業振興センター 試験事業部
EMC・安全技術グループ グループマネージャー
SiC、GaNデバイス等のパワー半導体の性能向上や、ノイズ規制の強化・対象機器の拡大などにより、パワエレ機器のノイズを正確に測定・評価することが難しくなってきています。
本セッションでは、最初にSiCパワーモジュールによる電磁ノイズ源の特性評価として、配線インダクタンス評価やモジュール近傍のノイズ分布の可視化技術について紹介します。次に、スイッチング特性に着目したノイズ発生メカニズム分析と抑制法について紹介します。最後に、規格認証試験において、正確にノイズ測定・評価するための注意点について事例を交えながら紹介します。
G3ADASからADSへ ISO26262のEMC
野島 昭彦
トヨタ自動車㈱ 電子制御基盤技術部 電波性能開発室 技範
1ADASに関するEMC国際法規及び国際規格の最新動向
- 自動車用EMC国際法規・国際規格の概要
- ADASに関するEMC国際法規・規格の動向
- ADASのEMC試験法について
吉田 秀樹
㈱本田技術研究所 四輪R&Dセンター 第9技術開発室 第5ブロック
2ADASからADSへの進化が及ぼす半導体EMIの特性変化
- 機能安全(ISO26262)対応によるLSIの変化
- ADASレベル3以上をサポートするSoCへのEMI影響
- 車載LSIにおける変化への取り組み
大峠 和夫
ルネサス エレクトロニクス㈱
インダストリアルソリューション事業本部 共通技術開発第一統括部
設計基盤技術開発第二部 課長
3
ADAS&Ethernet&LVDSのECU実装のEMC対応
- EthernetやCAN、CAN-FDに求められるEMC対策部品のトレンド
- ギガビットLVDS(差動およびCOAX)システムとEMC
- PoCシステムのEMC対策事例紹介
石橋 武友
TDK㈱ マグネティクスビジネスグループ
これからの自動車は、より安全で自由なとそのMobility Serviceを提供すべく、数多くのADAS(高度運転支援システム)の展開やADSにむけた開発が進んでいます。ここでは、構成するシステムは、ISO26262での機能安全を確保しつつ、国連の型式認証基準に適合していくことは必須となります。EMCは、各システムのハード設計の基本要件であり、国連の型式認証基準では、システム単位での適合しつつ車両システム全体での性能確保が必須となります。これらのシステム開発にかかわるすべてのエンジニアにたいして、自動車のエキスパートからは、これからのシステムに対するEMCの性能要件、基準、規格動向を紹介し、またそのEMC要件に適合させるために必要な、マイコンとマイコン実装時のフィルター設計に対して、それぞれのエキスパートからその対応技術の提案をいたします。
※自動車技術関連セッションG3セッションとの共通プログラムです。
G4
電動車両におけるEMC
舟木 剛
大阪大学 大学院 工学研究科 電気電子情報工学専攻
システム・制御工学講座 パワーシステム領域 博士(工学)
1各販売車両分解から見るEMC対策技術の現状と次世代自動車における最新EMC対策技術
- 三相インバータにおけるEMC対策技術(日産リーフ、トヨタカムリ、等)
- DC-DCコンバータ、バッテリ充電器におけるEMC対策技術(日産リーフ、プリウス、アウディSQ7等)
- 次世代自動車に要求されるEMC対策技術と最新EMC対策技術
山本 真義
名古屋大学 未来材料・システム研究所 /大学院 工学研究科
電気工学専攻 教授
2パワエレ機器のコンポーネント・車両EMC評価における計測課題とその対応(仮)
- 繰り返しインパルスノイズが計測器に与える影響と歪みスペクトルについて
- 自動車においてAMラジオ帯のノイズが、どのようにしてアンテナに伝搬するか
- 車載機器の評価において、基準電位の変動がもたらす影響について
鵜生 高徳
㈱デンソー 基盤技術開発部 EMC技術開発室 課長
3電動車両化の時代におけるECUのEMC設計への構え
- 電動車両化の時代に必要なノイズ対応
- ECU単体と自動車内でのシステム化に必要な対ノイズ設計
- 電磁遮蔽の実施およびその弊害に対する対応
前野 剛
㈱クオルテック EMC技術研究室 室長 博士(工学)
ハイブリッド自動車や電気自動車などの電動車両が一般的になってきました。ADASなどの情報通信機器が車両に多数搭載される一方で、電動車両におけるパワートレインでの高電圧・大電流のスイッチング動作は電磁雑音源となることが危惧されます。本シンポジウムでは車両から部品レベルに亘る広い観点で、電動車両におけるEMCの課題について述べます。
※自動車技術関連セッションG4セッションとの共通プログラムです。
G5
原理を学ぶ/事例に学ぶ : EMCシミュレーション
福本 幸弘
九州工業大学 大学院 工学研究院 電気電子工業研究系 特任教授
1SI/PI/EMIシミュレーション技術の変遷とその応用
- SI/PI/EMIシミュレーション技術の概要
- 先端的シミュレーション(CAE)技術
- 車載機器設計最適化への適用とAI技術の活用
浅井 秀樹
静岡大学 電子工学研究所 教授
2
モーメント法の活用術 ―基礎的なイミュニティの解析事例を通して―
- モーメント法の基礎
- BCI試験の解析
- ESD試験の解析
坪井 成文
㈱JSOL エンジニアリングビジネス事業部
3
モーメント法の勘所:電力線搬送通信(PLC)の放射ノイズ解析
- なぜモーメント法なのか?得意なところ・苦手なところ
- 放射ノイズを正しく計算するためのポイント・勘所
- オープンサイト実測結果との比較による精度検証
山本 竹志
パナソニック㈱ プロダクト解析センター 電気ソリューション部
メカトロデバイス設計課 熱流体設計係 係長
EMC設計にシミュレーション技術が導入されるようにってから20年以上経とうとしています。有限要素法、モーメント法、FDTD法など様々な電磁界解析手法がEMCシミュレーションに導入されるとともに、数多くの開発現場でシミュレータの活用が進んでいます。一方で、実際の製品開発(電子機器、デバイス、自動車など)において、EMCシミュレーションが測定に取って代わるというレベルには程遠い状況であることに変わりありません。
それでは、EMCシミュレーションの現状の実力とはどの程度のものなのでしょうか? また、シミュレータを有効に活用している現場は、どのような使い方をしているのでしょうか? 本セッションでは、大学、ツールベンダー、機器メーカーの第一人者から、これらの疑問に対する解説と事例の紹介を頂きます。
G6EMC設計・対策のツボをもっと押えよう
櫻井 秋久
日本アイ・ビー・エム㈱ 東京基礎研究所
IBMディスティングイッシュトエンジニア
1
プリント基板のEMC設計に盛り込むべきポイントと効果
~当たり前と思っていた基板設計、こんなところに大きな落とし穴が~
- プリント基板設計における問題点
- 問題の具体的な事例
- 解決方法と課題
久保寺 忠
㈱システムデザイン研究所 代表取締役
2
~IoT/自動運転など無線時代になぜ!?~ 今更聞けない!ケーブルのノイズ対策
- なぜ今更ケーブルのノイズ対策なのか?事例から見るノイズ対策のツボ!
- 各種素材から考える得意なところ不得意なところ
- この対策は正しいか?正しくないか?今更聞けない!ケーブルのノイズ対策事例
菊池 浩一
TDK㈱ Passive Application Center 担当課長
3IoT時代のイントラシステムEMC対策事例
- 電子機器自身のノイズにより、性能が劣化するイントラシステムEMC問題とは
- 無線機能を搭載した電子機器における無線の受信感度改善のためのノイズ対策事例紹介
坪内 敏郎
㈱村田製作所 EMI事業部 技術開発統括部 商品開発部
アプリケーション開発課
(1)回路基板は、不要電磁放射のエネルギー源であり、また伝達機能、アンテナ機能をあわせてもつことから、ここに技術的工夫を与えることで、不要電磁放射を大きく低減させることができます。ここでは効果が示された設計手法について詳しく議論します。(2)回路基板に電源線、通信線などをケーブルの形態で接続すると、大きな放射が発生することよく知られています。またこの放射を低減させるためにフェライトコアが大きな効果を示すこともよく知られています。この長きに亘り対策現場の救世主となり技術者を助けてきたフェライトコアについて、その基本特性、適用事例について議論します。(3)無線機能装備により製品のモビリティ化が始まると同時に、自分自身の不要放射などが自身の無線回路に飛び込み通信性能を劣化させるというイントラシステムEMC(俗:自家中毒)の問題が生まれ、多くの技術者を悩ませてきました。動作感度が大きく異なるものが近接して存在しなくてはならない状況の中で、どのような技術的工夫が考えられるのか議論します。