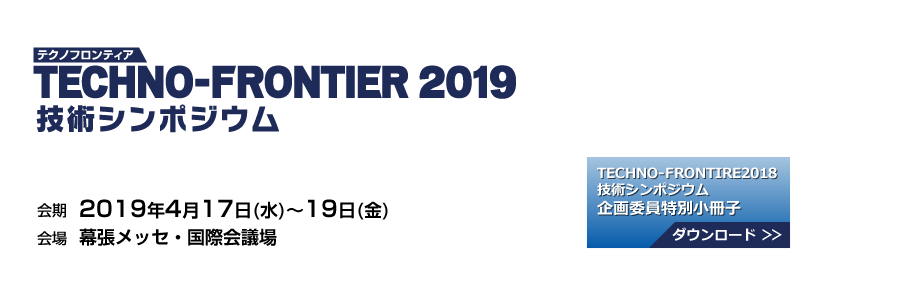※プログラム内容(スピーカ、コーディネータ、発表テーマ、内容等)が変更になる事がありますので予めご了承ください。

コーディネータ (敬称略)
小坂 卓
名古屋工業大学 大学院 電気・機械工学専攻 創造工学教育類
電気・機械工学教育類担当 教授
15相二重巻き線構造機電一体インホイールモータ
- 5相二重巻き線モータ
- 巻き線切り替え
- 機電一体構造
赤津 観
芝浦工業大学 工学部 電気工学科 教授
2
デュアルインバータによるオープンエンド巻線PMモータドライブ
- 総合効率の向上とフェールセーフを目指した新しい車載主機駆動システム
- デュアルインバータの空間ベクトル変調法とマルチレベル電圧波形の形成
- スイッチング状態の冗長性を活かしたマルチレベル電圧波形の形成とキャパシタ直流電圧源の制御
野口 季彦
静岡大学 教授
3多重3相インバータを用いた極数切替型誘導電動機
日高 勇気
三菱電機㈱ 先端技術総合研究所
自動車駆動用モータドライブシステムの主要部品は、バッテリとモータとパワーコントロールユニット(PCU)である。PCUの構成形態は種々あるが、その主構成部品であるVVVFインバータはモータに自在な可変速動作を付与し、高電圧供給を可能とする昇圧チョッパはモータ高速化による小型軽量化に貢献している。一方で、PCUはバッテリからモータへの急峻な出力変動を緩和するための緩衝材的な役割も担っている。これに対し、モータ自身も有限バッテリエネルギーの下で出来る限り走行距離を確保すべく、メモリーモータなど動作点に応じて一層の低損失化が期待できる可変磁束モータの開発が進められている。しかし、本来、モータとPCUは一体となって動作すべき部品であり、システム目標実現に際し、両者のWin-Winの関係を目指すべきである。
本セッションでは、電気部品としてのモータの入り口を巻線とし、結線方式を含めた巻線のあり様、例えば、ティースに巻かれた独立多数集中巻巻線、中性点を開いた三相オープン巻線、多相多重巻線など自由度を与え、それに対応する多重インバータとの組み合わせの最新研究開発事例を紹介する。第一線でご活躍の3名の講師をお招きし、従来用いられていないモータ巻線+PCU構成で新たなシステム機能を付与し、両者でWin-Winの関係を目指す将来のモータドライブシステムのあり方について議論する。
C1自動車用モータの新展開
梅野 孝治
㈱豊田中央研究所 システム・エレクトロニクス2部 部長
1電動化に向けた駆動用高出力モータの開発
- 自動車の電動化動向
- 駆動用高出力モータ
- 重希土類フリー磁石適用技術
黒木 次郎
㈱本田技術研究所 四輪R&Dセンター 第4技術開発室
第1ブロック 主任研究員
2
コアレス回転子形状を備えたフェライト磁石アキシャルギャップ型インホイールモータ
- フェライト磁石アキシャルギャップモータの特長
- 車載アプリケーションへの適用例
- 将来展望
竹崎 謙一
㈱ダイナックス 開発本部 電動システム開発部 部長
3変速機付きホイールハブモータ開発と走行中給電への取り組み
- 変速機を用いるモチベーション
- 変速機構と制御方法
- 走行中ワイヤレス給電への取り組み
郡司 大輔
日本精工㈱ パワートレイン技術開発部 副主務
地球環境問題に対応し、各国でHVやEVなどの電動化車両の普及が加速しています。こうした電動パワートレーンのキーとなる駆動用モータは従来よりラジアル型のIPMモータや誘導モータが使用されていますが、さらなる小型、高効率化、および、磁石の資源リスクへの対応に向けて、様々なチャレンジが行われています。本セッションでは、これらの取り組みの動向に関して、第一線でご活躍されている3名の講師の方に講演いただきます。まずは、本田技術研究所の黒木様より、重希土類フリー磁石を適用した高出力モータについて、ついで、ダイナックスの竹崎様より、フェライト磁石を用いたアキシャルギャップモータについてご紹介いただき、最後に、日本精工の郡司様より、変速機付きホイールハブモータについてご講演いただきます。いずれも従来の構造や概念を一新するモータであり、これからのモータ開発の指針を示すセッションとなっています。
※自動車技術関連セッションC1セッションとの共通プログラムです。
B2高速モータ(掃除機をモチーフとして)
関原 聡一
㈱東芝 研究開発本部 生産技術センター 制御技術研究部 部長
1
掃除機用モータの技術紹介
- 掃除機用モータの技術変遷
- 磁石モータ、SRモータなど各種モータの掃除機への適用例
- 機電一体化技術
加納 善明
大同大学 工学部 電気電子工学科 准教授
2各種クリーナと搭載モータ
- 背景(クリーナの市場動向など)
- 各種クリーナに搭載されているモータ
- ハイスピードDCモータ
押切 剛
東芝ライフスタイル㈱ クリーン事業部 技術部 主務
3
高性能なブラシレスDCブロアーモーター「JCモーター」
- クリーナーへの市場要求など
- モーター製造技術に関して
- 小型・軽量・超高速JCモーター
仲 興起
三菱電機㈱ コンポーネント製造技術センター
モーター製造技術推進 部長
様々な分野において、モータの回転数を高速化することにより、高性能、小型化する動きがあります。モータについては、材料や部品の進化、解析技術の高度化など、回路・制御については、マイコンやパワーデバイスをはじめとする半導体の進化、モータ制御技術の高度化などにより高速モータの実用化が進み、用途が拡大しています。
昨年は、この高速モータの先端技術として、自動車用モータを中心にご講演いただいたところ、大変ご好評をいただきました。今年は、家電製品の中でも近年モータの進化が著しい掃除機(クリーナ)用モータをモチーフに、各社の取り組みなどについてご講演いただきます。
高速モータに携わっておられる方は勿論、携わったことはないけれども興味を持っておられる方々にも有益な内容になっております。特に今回は家電製品用モータに関する内容ですので、より身近に感じていただけると思いますし、高性能なモータを安価に実現しているといった点でも興味深いと思います。
C2低振動・低騒音
野田 伸一
日本電産㈱ 中央モーター基礎技術研究所 研究第1部 部長 工学博士
1圧縮機用永久磁石同期モータの低振動化
- モータの振動・騒音対策の考え方
- 圧縮機用モータの振動・騒音の評価事例
高畑 良一
㈱日立製作所 研究開発グループ 電動機材料研究部 主任研究員
2IoTを応用したモータの振動測定方法と診断技術
平手 利昌
東芝産業機器システム㈱ 技術企画部 要素技術開発担当
3低騒音モータの開発
- モータの振動騒音発生要因
- 騒音対策方法の提案
- 騒音低減効果
吉桑 義雄
三菱電機㈱ 先端技術総合研究所 自律制御システム開発プロジェクト
自動運転システムグループマネージャ
モータは、洗濯機、エアコンなど家電製品、一般産業用、工作機械や医療機器、さらには最近では電気自動車(EV)が注目され、幅広く使用されています。モータの歴史は古く、その間に小型、軽量、高速、高効率などの幾多の技術改良がなされてきました。しかし、今日でも技術上の困難な課題はいくつか残されており、その一つとして、振動・騒音の問題があります。
本セッションでは、振動発生源である電磁力の要因である偏心高調波やインバータ高調波、それに対しての低騒音化技術について適用事例を交えて発表していただきます。次に「モータの基礎的な振動・騒音計測技術」と「IoTを応用したモータ振動・騒音・電流の計測技術による診断方法」の事例を紹介いただきます。本セッションは、メーカの第一線で活躍されている専門家の方々より「モータ振動騒音問題を解決する手掛かりとなる」ノウハウが多く詰まった有益な情報が得られる内容です。
B3永久磁石 ~モータの新しい試み~:新構造モータ(ボンド磁石)
渡邊 賢司
㈱安川電機 技術開発本部 開発研究所
モータ・アクチュエータ技術部長
1Sm-Fe-N系ボンド磁石適用によるアモルファスモータの高出力化
- アモルファス金属の特徴およびモータへの適用方法
- 磁石材料の選定
- モータ特性の評価
出口 見多
㈱日立製作所 研究開発グループ ドライブシステム制御研究部 研究員
2高性能圧粉磁心を搭載した薄型・高トルクなアキシャルギャップモータ
- 高磁束・低ロスな圧粉磁心
- 薄型・高トルクのアキシャルギャップモータ
- 圧粉磁心の最新開発動向
齋藤 達哉
住友電気工業㈱ アドバンストマテリアル研究所
3ハルバッハ磁石配列応用IPMSMの減磁耐力向上
- 集中巻IPMSMの減磁耐力
- 斜め配向着磁IPMSM
- ハルバッハ磁石配列の応用
西山 典禎
パナソニック㈱ アプライアンス社 冷熱空調デバイス事業部 主幹技師
家電・ロボット・自動車等のアプリケーションにより、モータに求められる要求仕様(特性・効率・形状・コスト等)は異なります。このため、要求仕様に対応する様々なモータが開発・製品化されています。また、モータの性能向上に欠かせない高性能の磁石・軟磁性材料を活用し、さらにその材料配置を工夫した新構造のモータが開発されています。
本セッションでは、ボンド磁石・アモルファス金属を採用したモータ、圧粉磁心を採用した薄型アキシャルギャップモータ、さらに磁束集中によりモータ高出力化を実現するハルバッハ構造のモータについて紹介します。
本セッションが聴講される皆様のモータ開発やモータ活用の一助となれば幸いです。
C3見直されるIM
藤綱 雅己
㈱デンソー 技術企画部 担当部長・技師
1
誘導機関係
千葉 明
東京工業大学 教授
2車載応用に向けた高温超伝導誘導モータの開発
- 誘導機の超伝導化
- 非線形超伝導特性と回転特性
- 回転機システム最適化
中村 武恒
京都大学 大学院 工学研究科 電気工学専攻 特定教授
3誘導電動機の銅損最小化制御
- 誘導機のベクトル制御
- 誘導機の銅損最小化制御
- 誘導機の高速駆動時の安定化
加藤 尚和
長岡モーターディベロップメント㈱ 取締役
全世界で年間1億台近い自動車生産の内、EV、PHEV及びHEVなどの電動車は、2017年時点では42万台(約5%)ですが、2035年には14倍の6000万台以上(50%)へ急拡大が予想されています。
2008年からのレアアース問題は、価格も安定化し、Dy(ジスプロシウム)フリー技術や粒界拡散合金など省Dy技術も完成しましたが、今後の電動車の急拡大に比例して、希土類磁石の必要量が増加するため根本的な安定供給問題は解決されていません。このような背景の中、磁石を必要としない誘導モータは見直されており高性能化が進んでいます。今回は、誘導モータの研究の中で最新の話題3つを取り上げました。
初めに、自動車用誘導モータ、設計のネックとなる電磁界解析法及びパフォーマンスを紹介して頂きます。次に究極の車載応用に向けた高温超伝導誘導モータの開発について、最後に誘導モータの最大損失である銅損の最小化制御について具体的に解説して頂きます。全て、実際の研究に携わっておられる第一人者自らのご講演であり、皆様の誘導モータの更なる高性能化を検討する機会となることを期待します。
B4鉄心や磁石に新しい試みを導入したPMモータ
三木 一郎
明治大学 理工学部 電気電子生命学科 専任教授
1自動車駆動用IPMSMの出力密度向上と高効率化
- 小型・高速化による出力密度向上
- 低鉄損材料の適用による高効率化
- 強磁力磁石の適用による性能と機械強度の両立
真田 雅之
大阪府立大学 大学院 工学研究科 電気・情報系専攻 准教授
2
高Bsナノ結晶合金を採用した究極高効率モータの開発
- 産業用アモルファスモータの開発経緯
- 高Bsナノ結晶合金の磁気特性
- 高Bsナノ結晶合金を採用したモータの試作評価結果
榎本 裕治
㈱日立製作所 研究開発グループ 材料イノベーションセンタ
電動機材料研究部 材料E2 主任研究員
3永久磁石と鉄心の最適化によるIPMモータの特性改善
- 有限要素法を基盤とした最適化手法
- 分布巻及び集中巻IPMモータへの適用
- 実機試作検証結果
山崎 克巳
千葉工業大学 工学部 電気電子工学科 教授
グローバルな問題として地球温暖化問題があります。これを解決するための一方策として、世界中の産業やエコカーに用いられている非常に多くのモータの特性改善、特に高効率化が進められています。これまでの努力で徐々に目標に近づいてきていますが、さらに高レベルな目標を達成するためにはブレークスルーが必要と思われます。
本セッションでは、まず自動車駆動用IPMSMに低鉄損材料と強磁力磁石を適用した場合の特性について紹介していただきます。次に、驚異的な効率特性を示す高Bsナノ結晶合金を採用したモータについて解説していただきます。そして、最後に磁石と鉄心を最適化したIPMSMの特性評価について講演していただきます。本セッションへの参加がモータの進化をさらに促すアイデア提供の機会となることを期待します。
C4センサレス・ドライブ制御技術の進化
森永 茂樹
アイダエンジニアリング㈱ 参与 開発本部
1センサレス制御技術の今までとこれから
- センサレス制御技術,何ができて何ができないのか
- 停止・低速域でも利用可能な新しい拡張誘起電圧 EEMFω+h
- 切替を必要としない・応答を犠牲にしない・モータを選ばない位置センサレス制御にむけて
道木 慎二
名古屋大学 大学院 工学研究科 情報・通信工学専攻 教授
2
永久磁石同期モータの位置センサレス制御方式の分類と高応答化
- 位置検出方式の分類
- 高応答化手法の分析
- 高応答化システムの構築
正木 良三
SunDAS
3
高精度駆動を実現するモータ制御技術
- 高精度駆動のための高応答制御
- 高精度駆動のためのロストモーション補正
- 機械先端点の振動抑制
鴻上 弘
ファナック㈱ FA事業本部 サーボ研究所 技師長
近年、半導体の進歩により、マイコンの演算パワーが著しく高くなり、機器の性能に大きく寄与している。そこで、過去にマイコンの演算パワーの不足で、性能が出せなかったセンサレス・ドライブ制御方式などを見直し、モータ制御の高応答化、高精度化を実現するその制御技術の進化について取り上げます。
先ず、センレス制御技術歴史をたどり、これからのセンサレス制御技術の方向性を紹介します。次に、広く採用されている永久磁石同期モータを高性能化できるセンサレス制御方式の高応答化について説明し、最後に、高精度駆動を実現するドライブ技術について紹介します。
以上、本セッションが、今後のモータ制御の性能向上を目指す開発の一助となれば幸いです。
B5次々世代パワーデバイス最新技術動向
西岡 圭
大阪大学 大学院 工学研究科 SiC応用技術共同研究講座 特任研究員
1β-Ga2O3パワーデバイス最新技術動向
- β-Ga2O3パワーデバイスの魅力
- β-Ga2O3単結晶基板・エピ開発動向
- β-Ga2O3パワーデバイス開発動向
佐々木 公平
㈱ノベルクリスタルテクノロジー 開発部長
2α-Ga2O3パワーデバイス最新技術動向
- Ga2O3パワーデバイスの位置付け
- ミストCVD法によるα-Ga2O3 SBD
- MOSFETのノーマリオフ動作実証
四戸 孝
㈱FLOSFIA 取締役CTO
3ダイヤモンドパワーデバイス最新技術動向
- パワーデバイスにおけるダイヤモンドの特性・応用等の期待
- ウェハ開発状況
- デバイス開発状況
鹿田 真一
関西学院大学 教授
次世代パワーデバイス新材料であるSiCとGaNは、ご存知のようにそれぞれが得意とする応用分野で続々と実用化されています。
そして早くも次の「次々世代」パワーデバイス新材料として期待されているのが酸化ガリウムや究極の半導体材料と言われているダイヤモンドで、特に酸化ガリウムはSiCより高性能で生産コストも抑えられる材料として期待されています。また、酸化ガリウム結晶構造の中でも、β型(βガリア構造)とα型(コランダム構造)が先行しており、α型酸化ガリウムSBDの量産が間近に迫ってきています。このセッションでは、これら次々世代パワーデバイスの最新技術動向を取り上げます。本セッションが各位の新世代パワーデバイスを用いた商品の開発スピードアップに繋がれば幸いです。
C5高性能化を支えるモータ巻線技術 パートⅡ
菰田 晶彦
㈱デンソー モータ技術2部 担当課長
1
集中巻分割コアモータの連続角線巻線技術
- コア分割形態の比較検討
- 分割コアの連続巻技術
- 分割コアの連続角線巻線技術
石上 孝
㈱日立製作所 研究開発グループ 主任研究員
2高密度コイルについて
- 高密度巻線技術
- 平角α積層高密度コイル
- 高密度圧縮成型コイル
小林 延行
㈱セルコ 代表取締役
3ASTコイル開発の最新動向
- 量産化を可能にする技術
- モーターコイル概念へのチャレンジ
本郷 武延
㈱アスター 代表取締役
モータ技術シンポジウムでモータの「巻線技術」を取り上げるのは、昨年(2018年)に引き続き2年連続です。
昨年の同シンポジウムでは想像以上に大勢の方にご参加頂き、「巻線」に対する関心の高さに驚きました。
「巻線」は既に熟成したように思われがちですが、今なお着実に進化し続け、近年のクルマ社会において、電動化が注目される中、今まで以上にモータの小型化、高効率化を支える重要な要素となっています。
本セッションでは、最新の巻線の市場動向や技術動向について取り上げる。
小型・高効率なモータを実現する究極の高密度で革新的な平角等の巻線の技術についても紹介する。
本講演が、巻線技術の進展状況を知るとともに、モータの更なる高性能化の可能性を検討する機会となることを期待します。
B6ロボット
長竹 和夫
(公財)NSKメカトロニクス技術高度化財団 評議員
1
モータ性能の向上と次世代ロボット
- アクチュエータに起因するロボットの性能の限界
- モータ性能とロボット性能について
- ロボットから見た次世代アクチュエータへの期待
小菅 一弘
東北大学 大学院 工学研究科 教授
2バックドライブ可能なロボット用アクチュエータ
- バックドライバビリティを実現するアクチュエータの最新動向
- バックドライバビリティを実現するバイラテラルドライブギヤの紹介
- バックドライバビリティを実現するスパイラルモータの紹介
藤本 康孝
横浜国立大学 工学研究院 教授
3産業用ロボットのモータ・ドライブ技術
- ロボットの市場動向
- 産業用ロボットのモータ技術
- 産業用ロボットのドライブ技術
渡邊 賢司
㈱安川電機 技術開発本部 開発研究所
モータ・アクチュエータ技術部長
人間を支援するロボットの話題が連日のように報道され、全世界で賑わいを見せています。
わが国のロボット関連技術は、産業用途を中心に世界をリードしており、民生分野においてもガイダンス、サービスロボットが実用化され、ここ数年現場で活用が始まっています。
本セッションでは、ロボット開発分野の先端で活躍されている先生方に、業界の動向、普及の向けた期待・課題や、モータ・ドライブへの期待、ロボット駆動に特化したアクチュエータ、モータ、サーボドライブ技術の動向につきご講演戴きます。
聴講される方々が、よりロボット分野の現状、課題を理解戴けると信じます。
C6絶縁・評価、電機品新材料
相馬 憲一
㈱日立産機システム
テクノロジーアドバイザー・研究開発センタ長付 工学博士
1
インバータ駆動モータにおける放電のメカニズムと測定方法、絶縁評価
- パワエレ技術による省エネ対策や電気自動車に用いられているインバータ駆動モータの絶縁技術
- インバータサージによって発生する複雑な部分放電のメカニズム
- モータ巻線や絶縁シート材料のインパルス試験、測定方法と絶縁評価
永田 正義
兵庫県立大学 大学院 工学研究科 電気物性工学専攻 教授
2電機品イノベーション向け新材料開発
- 日立化成の樹脂技術
- 電気絶縁ワニスの役割と開発状況
- マイカテープの役割と高放熱タイプの開発状況
稲田 禎一
日立化成㈱ 樹脂材料事業部 主管研究員・博士(工学)・博士(学術)
3カーエレクトロニクス絶縁材料としてのポリイミドフィルムの応用
- ポリイミドフィルムの耐熱・絶縁特性およびエレクトロニクス用途の紹介
- ポリイミドフィルムを用いた産業用・電鉄車輌用モータ絶縁システム
- カーエレクトロニクスへのポリイミドフィルムの応用
~小型・高効率・高出力化と絶縁信頼性・熱・ノイズ問題の両立~
米長 修
東レ・デュポン㈱ カプトン営業部 マーケティング課 課長
HEV、EVなどカーエレクトロニクスは急速に進展し、そこに使用されるパワエレ・ドライブシステムは小型・高密度化、高電圧化されている。これは自動車にとどまらず、産業機械や車両、家電類も同じ傾向である。電機品の信頼性向上には、短時間に発生する高電圧インパルスの測定・評価による放電メカニズムの解明、それに従う絶縁システム、さらには耐熱性やノイズ対策などを兼ね備えた新たな材料とその利用技術が重要なテーマである。このセッションでは「絶縁・評価、電機品新材料」として、インバータ駆動モータ絶縁の課題や電気学会を中心とした国際標準化の動き、材料では絶縁ワニスの過去を振り返りながら今後いっそうの応用が期待されているポリイミドフィルムの開発状況を紹介する。