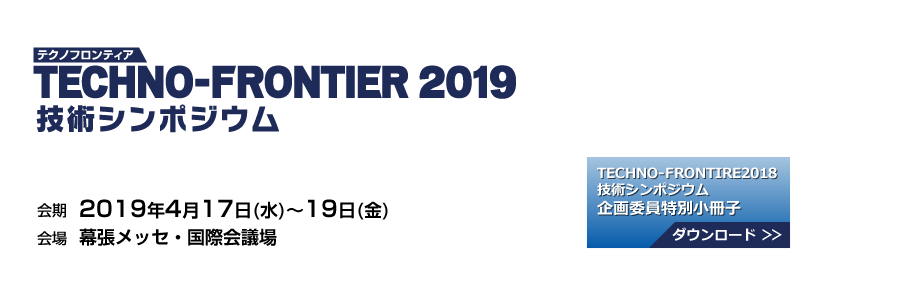※プログラム内容(スピーカ、コーディネータ、発表テーマ、内容等)が変更になる事がありますので予めご了承ください。

コーディネータ (敬称略)
梅野 孝治
㈱豊田中央研究所 システム・エレクトロニクス2部 部長
1電動化に向けた駆動用高出力モータの開発
- 自動車の電動化動向
- 駆動用高出力モータ
- 重希土類フリー磁石適用技術
黒木 次郎
㈱本田技術研究所 四輪R&Dセンター 第4技術開発室
第1ブロック 主任研究員
2
コアレス回転子形状を備えたフェライト磁石アキシャルギャップ型インホイールモータ
- フェライト磁石アキシャルギャップモータの特長
- 車載アプリケーションへの適用例
- 将来展望
竹崎 謙一
㈱ダイナックス 開発本部 電動システム開発部 部長
3変速機付きホイールハブモータ開発と走行中給電への取り組み
- 変速機を用いるモチベーション
- 変速機構と制御方法
- 走行中ワイヤレス給電への取り組み
郡司 大輔
日本精工㈱ パワートレイン技術開発部 副主務
地球環境問題に対応し、各国でHVやEVなどの電動化車両の普及が加速しています。こうした電動パワートレーンのキーとなる駆動用モータは従来よりラジアル型のIPMモータや誘導モータが使用されていますが、さらなる小型、高効率化、および、磁石の資源リスクへの対応に向けて、様々なチャレンジが行われています。本セッションでは、これらの取り組みの動向に関して、第一線でご活躍されている3名の講師の方に講演いただきます。まずは、本田技術研究所の黒木様より、重希土類フリー磁石を適用した高出力モータについて、ついで、ダイナックスの竹崎様より、フェライト磁石を用いたアキシャルギャップモータについてご紹介いただき、最後に、日本精工の郡司様より、変速機付きホイールハブモータについてご講演いただきます。いずれも従来の構造や概念を一新するモータであり、これからのモータ開発の指針を示すセッションとなっています。
※モータ技術シンポジウムC1セッションとの共通プログラムです。
H1自動運転を支えるセンシング技術①
井上 秀雄
神奈川工科大学 創造工学部 自動車システム開発工学科 学科長
教授 / 先進自動車研究所長&自動車工学センター長
1運転支援・自動運転における安全技術の進化について
- リスク予測制御(Risk predictive control)
- 人間機械協調制御(Shared control)
- Virtual & Real の評価環境
井上 秀雄
神奈川工科大学 創造工学部 自動車システム開発工学科 学科長
教授 / 先進自動車研究所長&自動車工学センター長
2
NVIDIA DRIVEとセンシング
- NVIDIAの自動運転における活動
- センサとAIの最新状況
- 今後に向けて
廣瀬 一人
NVIDIA Automotive Business Development Manager
3高度運転支援・自動運転を支えるセンシング技術
- 各種車載周辺監視センサの概要
- センサーフュージョンの事例紹介
- 自動運転の事例紹介
青木 豊
㈱デンソー 先進モビリティシステム開発部 担当課長
※センシング技術シンポジウムH1セッションとの共通プログラムです。
D2パワーエレクトロニクス技術が未来を創るxEVのロードマップ
藤本 博志
東京大学 大学院 新領域創成科学研究科
先端エネルギー工学専攻 准教授
1日産の電動パワートレイン技術と将来動向
- 日産の電動パワートレイン戦略
- 新型電気自動車「日産リーフ」の技術
- 電動パワートレイン拡大の方向性
小野山 泰一
日産自動車㈱ パワートレイン・EV技術開発本部 エキスパートリーダー
248V電動化技術
- 48V電動化システムの動向と将来予測
- 48V電動化システムの概要
- 48V電動化システムの効果
清田 茂之
ボッシュ㈱ パワートレインソリューション事業部
電動パワートレインコンポーネント開発部 ゼネラルマネージャー
3
電動化を支える電力変換技術
- EV-PHVの主機用インバータ技術
- オンボート・急速受電における電力変換技術
- ワイヤレス充電における電力変換技術
伊東 淳一
長岡技術科学大学 大学院 工学研究科 教授
自動車の電動化が急速に進む今、最終的な製品としての自動車、それを支えるシステム・部品技術、回路・制御技術の各要素は大きな転換期を迎えている。本セッションではそれぞれの動向・最前線を自動車会社、総合サプライヤ、大学のキーパーソンからご講演いただく。
日産自動車・小野山様からはEVとe-POWERを基軸とした取り組み、自動車の電動化に必要なテクノロジーを大局的にご紹介いただく。ボッシュ・清田様からは48V電動化技術の動向と方向性、それに対する技術ソリューションをご紹介いただく。長岡技術科学大学・伊東先生からは自動車の電動化を支えるパワーエレクトロニクス技術の最新動向と将来へのタネとなる新たな技術をご紹介いただく。
本セッションを通じて、パワーエレクトロニクス技術の最前線が創るxEVの体系的なロードマップを示したい。
※電源システム技術シンポジウムD2セッションとの共通プログラムです。
H2自動運転を支えるセンシング技術②
井上 秀雄
神奈川工科大学 創造工学部 自動車システム開発工学科 学科長
教授 / 先進自動車研究所長&自動車工学センター長
1ボッシュの自動運転への取組み
- 自動車を取り巻く社会を形作るメガトレンド
- 社会の変化に合わせた将来のモビリティのあり方
- 自動運転に必要とされる要素技術
千葉 久
ボッシュ㈱ シャシーシステム コントロール事業部 システム開発部門
自動運転システム開発部 部長
2「みちびき」対応受信機の自動運転向けセンサとしての活用について
- 「みちびき」対応受信機の農機の自動運転への活用
- 「みちびき」対応受信機のドローンの自動運転への活用
- 衛星測位が難しい場面での位置情報提供のための取り組みについて
大西 健広
マゼランシステムズジャパン㈱ 開発部 サイエンティスト
3Intempora 社 RTMaps による自動運転向けアプリケーションのグラフィカルな試作開発
- ADAS/自動運転分野の開発の課題
- RTMaps(Real-time Multi-sensor Applications)によるセンサフュージョンアルゴリズムの
プロトタイピング
- RTMaps を軸にした自動運転開発へのモデルベース開発への展開
山田 崇
dSPACE Japan㈱ ソリューション技術部
シニアプロダクトコーディネータ
※自動車技術関連セッションH2セッションとの共通プログラムです。
E3自動車の電動化戦略
佐藤 登
エスペック㈱ 上席顧問 / 名古屋大学 未来社会創造機構 客員教授
1
電動車両開発の取り組みとアウトランダーPHEVの進化
- 環境政策の強化と電動車両の普及
- 三菱自動車での電動車両開発の取り組み
- アウトランダーPHEVの進化
半田 和功
三菱自動車工業㈱ EV・パワートレイン開発マネージメント部
マネージャー
2
電動車普及とその課題
- 温暖化ガス削減の目的で電動車両の普及が求めれている
- 電動車両の普及のためには電池性能の向上、車両コストやインフラの整備等の
多くの課題が残されている
- これらの課題と取組内容の概要を述べる
野口 実
本田技研工業㈱ 標準化推進部
3
電動化と知能化が拓くインテリジェンスモビリティの時代
- 日産が他社に先駆け推進している“Nissan Intelligent Mobility”の下での“電動化・知能化”
- 航続距離を飛躍的に伸ばしたLEAF e+の主な機能と性能
- 将来のエネルギー動向。
久村 春芳
日産自動車㈱ フェロー
2018年から一段と強化された米国ZEV規制、そして19年から始まった中国NEV規制、さらには21年から発効する欧州CO2規制と、自動車業界にとっては開発負荷が格段に増大しています。一方、欧州を中心に今後、ディーゼ車やガソリン車の販売規制などが計画されている中で、自動車の電動化は避けては通れません。
これまで日本の自動車業界が世界のリーダーとして、HEV、PHEV、EV、FCVを市場に供給してきました。一方、近年はドイツ勢がブランド力と投資力を武器に日系の競合社として存在感を示してきています。
そういう中にあって、日系勢も開発強化に余念がありません。PHEVでは高い評価を得てきた三菱自動車は、商品競争力を訴求しています。ホンダは全方位の電動化戦略のもと、HEVとPHEVを中心に電動化路線を描いています。日産自動車は2010年のリーフでEV領域を先導し、更にはシリーズHEVでのラインナップを図っています。
本セッションでは、話題性のあるこの3社の電動化戦略と電池開発戦略について解説いただきます。
※バッテリー技術シンポジウムE3セッションとの共通プログラムです。
G3ADASからADSへ ISO26262のEMC
野島 昭彦
トヨタ自動車㈱ 電子制御基盤技術部 電波性能開発室 技範
1ADASに関するEMC国際法規及び国際規格の最新動向
- 自動車用EMC国際法規・国際規格の概要
- ADASに関するEMC国際法規・規格の動向
- ADASのEMC試験法について
吉田 秀樹
㈱本田技術研究所 四輪R&Dセンター 第9技術開発室 第5ブロック
2ADASからADSへの進化が及ぼす半導体EMIの特性変化
- 機能安全(ISO26262)対応によるLSIの変化
- ADASレベル3以上をサポートするSoCへのEMI影響
- 車載LSIにおける変化への取り組み
大峠 和夫
ルネサス エレクトロニクス㈱
インダストリアルソリューション事業本部 共通技術開発第一統括部
設計基盤技術開発第二部 課長
3
ADAS&Ethernet&LVDSのECU実装のEMC対応
- EthernetやCAN、CAN-FDに求められるEMC対策部品のトレンド
- ギガビットLVDS(差動およびCOAX)システムとEMC
- PoCシステムのEMC対策事例紹介
石橋 武友
TDK㈱ マグネティクスビジネスグループ
これからの自動車は、より安全で自由なとそのMobility Serviceを提供すべく、数多くのADAS(高度運転支援システム)の展開やADSにむけた開発が進んでいます。ここでは、構成するシステムは、ISO26262での機能安全を確保しつつ、国連の型式認証基準に適合していくことは必須となります。EMCは、各システムのハード設計の基本要件であり、国連の型式認証基準では、システム単位での適合しつつ車両システム全体での性能確保が必須となります。これらのシステム開発にかかわるすべてのエンジニアにたいして、自動車のエキスパートからは、これからのシステムに対するEMCの性能要件、基準、規格動向を紹介し、またそのEMC要件に適合させるために必要な、マイコンとマイコン実装時のフィルター設計に対して、それぞれのエキスパートからその対応技術の提案をいたします。
※EMC設計・対策技術シンポジウムG3セッションとの共通プログラムです。
E4車載用電池
小林 弘典
産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門
総括研究主幹
1
Next generation anode materials for EV application
- Silicon anode material
- New conducting material (CNT、Graphene)
- New Binder for Silicon anode
Je Young Kim
Research Fellow LG Chem
2
ハイブリッド自動車用リチウムイオン電池の小型・高出力化
- 日立の車載用リチウムイオン電池の実績
- 技術の特徴と電池特性
- 高出力48V電池パック
板橋 武之
ビークルエナジージャパン㈱ 設計開発本部 副本部長
3車載用電池試験の最新動向と事例紹介
- 認証・規格の最新動向
- 電池試験の最新動向
- 組電池の試験事例
久世 真也
エスペック㈱ テストコンサルティング本部
バッテリー安全認証センター 主事
近年、中国で電気自動車(EV)が急激に導入されてきましたが、欧州連合での二酸化炭素排出量の規制強化に伴い、欧州の自動車メーカが今年度相次いで新型電動車両の販売をアナウンスするなど、電動車両普及に向けた主戦場が欧州に移りつつあります。車載用電池の駆動電源はリチウムイオン二次電池ですが、ハイブリッド自動車(HEV)では出力密度重視、EVではエネルギー密度重視となるため、電池の構成材料及び設計が異なっています。EV用としては更なるエネルギー密度の向上が期待されており、負極材料の開発動向が鍵を握っています。また、搭載の容量が増大するに伴い、安全性への懸念が増大してきています。
本セッションでは、「ハイブリッド自動車用リチウムイオン電池の小型・高出力化」、「EVアプリケーションにおける次世代負極素材」並びに「車載用電池試験の最新動向と事例紹介」について、最新の国内外の動向についての情報を得ることができます。これらの講演から、車載用LIB開発の最前線での技術動向について理解することができ、今後の技術開発に役に立てることができます。
※バッテリー技術シンポジウムE4セッションとの共通プログラムです。
G4
電動車両におけるEMC
舟木 剛
大阪大学 大学院 工学研究科 電気電子情報工学専攻
システム・制御工学講座 パワーシステム領域 博士(工学)
1各販売車両分解から見るEMC対策技術の現状と次世代自動車における最新EMC対策技術
- 三相インバータにおけるEMC対策技術(日産リーフ、トヨタカムリ、等)
- DC-DCコンバータ、バッテリ充電器におけるEMC対策技術(日産リーフ、プリウス、アウディSQ7等)
- 次世代自動車に要求されるEMC対策技術と最新EMC対策技術
山本 真義
名古屋大学 未来材料・システム研究所 /大学院 工学研究科
電気工学専攻 教授
2パワエレ機器のコンポーネント・車両EMC評価における計測課題とその対応(仮)
- 繰り返しインパルスノイズが計測器に与える影響と歪みスペクトルについて
- 自動車においてAMラジオ帯のノイズが、どのようにしてアンテナに伝搬するか
- 車載機器の評価において、基準電位の変動がもたらす影響について
鵜生 高徳
㈱デンソー 基盤技術開発部 EMC技術開発室 課長
3電動車両化の時代におけるECUのEMC設計への構え
- 電動車両化の時代に必要なノイズ対応
- ECU単体と自動車内でのシステム化に必要な対ノイズ設計
- 電磁遮蔽の実施およびその弊害に対する対応
前野 剛
㈱クオルテック EMC技術研究室 室長 博士(工学)
ハイブリッド自動車や電気自動車などの電動車両が一般的になってきました。ADASなどの情報通信機器が車両に多数搭載される一方で、電動車両におけるパワートレインでの高電圧・大電流のスイッチング動作は電磁雑音源となることが危惧されます。本シンポジウムでは車両から部品レベルに亘る広い観点で、電動車両におけるEMCの課題について述べます。
※EMC設計・対策技術シンポジウムG4セッションとの共通プログラムです。
F5電動化における熱設計(カーエレ・パワエレ)
三輪 誠
㈱豊田自動織機 エレクトロニクス事業部 技術部 開発統括室 室長
1車載電子製品の実装・熱設計技術
- 車両の電動化、電子化の加速により車載搭載システムが増加
- 燃費向上のために電子製品には、小型化とさらに高信頼性を求められている
- 熱設計は、小型実装と高信頼性実現の両方を実現するように進化している
神谷 有弘
㈱デンソー 基盤ハードウェア開発部
2シミュレーションによるモータの熱と騒音の検討
- 顧客ニーズの多様化に伴い、モータは本来の性能に加え低騒音化も重要
- 空冷方式モータの低騒音化には、騒音とトレードオフとなる熱の考慮も必要
- シミュレーションにて構造を検討し、機能試作機にて効果を確認
金子 公寿
富士電機㈱ 技術開発本部 イノベーション創出センター
デジタルエンジニアリング部 主査
3JMAG-Designerを使用した高調波損失計算と、
FloTHERMを使用した熱流体解析の連携による、車載モータの発熱計算手法
- モータ制御による電流高調波を考慮した鉄損解析
- JMAG-Designerにより出力された損失分布を熱ソースとして利用
- FloTHERM (XT) による熱流体解析
河治 学
アイシン精機㈱ 走行安全技術部
益々加速化する電動化への対応及び小型化への要求に対し、熱対策は様々な要因が複雑に絡み合い、単独での解決が大変困難になっており、特にカーエレ・パワエレ分野ではその傾向が顕著に現れています。
本セッションでは、「電動化における熱設計」と題して、カーエレ・パワエレ分野で必要とする小型高信頼性の両立とモータの発熱対策をテーマに3名の方に設計者の立場でお話しして頂きます。
上記3事例をご参考にして頂き、現状の問題解決の一助になれば幸いです。
※熱設計・対策技術シンポジウムF5セッションとの共通プログラムです。